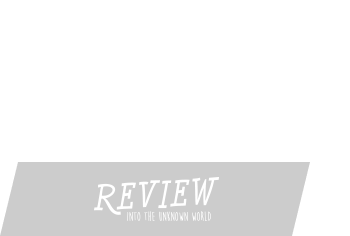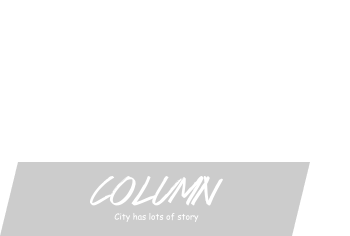第7回「スナックよね。」開催!テーマは「’80s〜現在の原宿とファッションカルチャー」
編集者・フォトグラファーの米原康正さんが様々なゲストを迎え、原宿のストリートカルチャーをひも解くトークイベント「スナックよね。」。第7回のテーマは「’80s〜現在の原宿とファッションカルチャー」。ゲストは「HYSTERIC GLAMOUR(ヒステリックグラマー)」の設立者でありクリエイティブディレクターの、北村信彦さん。多くの海外ミュージシャンとの交流があることでも知られる。2人が振り返る当時のファッションカルチャー、そして当時のオモハラとは?
何もかもモチベーションは「音楽」にあった
米原「今日のゲストは北村信彦さんです。ヒステリックグラマー立ち上げ当時から今までについて色々聞いてみたいと思います」
北村「よろしくお願いします」
米原「何度も聞かれているかとは思うけど、ブランド名の由来って?」
北村「まず、あんまり日本語に訳せないのがいいかなって思って。辞書で色々単語調べて書いていって、『ヒステリック』も『グラマー』も、どっちもちょっと日本語に訳しづらいじゃないですか、それでいてヒステリックでグラマーな女性っていうのもあんま想像つかないし」
 米原康正さん(左)と北村信彦さん(右)
米原康正さん(左)と北村信彦さん(右)
米原「それでブランド始めると、すぐに人気が出たよね」
北村「84年の6月に正式に入社して、そこから1回目の展示会が7月かな。本当に1ヶ月ちょっとでコンセプト決めてデザインして、40〜60点くらいサンプルを作って。そしたら、その当時『Olive(オリーブ)』っていう雑誌がすごい若い子たちにウケてたんだけど、そこの編集長が展示会初日の一番最初に来てくれたの。でも10分くらいサーっと見て帰っちゃったんですよ。だからちょっと落ち込んでたら、その日の夜に電話があって『実は明日から次の号の撮影でパリに行くんですけどサンプルお借りできますか?』って言われて。次の日もその次の日も展示会あったけど、雑誌に載った方が絶対効果あるって思ったから、貸した商品は、ポラロイドで撮った写真飾ったりして。だから2日目以降の展示会は、ほとんどポラロイド写真の展示だったんです(笑)」
米原「来る人みんなポラロイドしか見てないの?(笑)」
北村「そうそう。結構地方からも来るから、来る人みんな『ナメてんのか?』って怒っちゃって(笑)。そこから1、2ヶ月くらい経ってオリーブが届いたんですよ。それで見たら巻頭の方でうちのブランドを使ってくれてて、それが本屋に並んでからは、かなり電話がかかって来て、展示会で怒って帰っちゃった人からも連絡来ましたね(笑)。そんな感じでかなりいい感じのスタートだった」
米原「いきなりのスタートダッシュだよね」
 北村「かなりラッキーだったなっていうのはありますね」
北村「かなりラッキーだったなっていうのはありますね」
米原「でも元々は、オリーブを目指してたわけじゃないでしょ?」
北村「うん、全然目指してない。まぁ当時の最終目的って、自分が好きなミュージシャンと何か仕事ができたらいいなってところだったから。洋服に興味があったのも、デザイナーブランドとかパリコレとかには興味があったんじゃなくて、自分の好きなミュージシャンが着ている服を見て同じの欲しいなとかだったんだよね。だから専門学生の時も、ちょうどコムデギャルソンとかヨウジヤマモトとかDCブランド全盛の時代で、一時はそっちにもいくんだけど結局自分よりも似合うやついるし、俺がこれ買ってもなぁって思ってた」
米原「その当時はどんな格好してたの?」
北村「俺はどっちかっていうと古着だね。古着屋回って1点物を探すとかのが多かったかな」
米原「古着屋はどの辺行ってたの?」
北村「いや、もう本当この辺り(原宿)。竹下通りの中の赤富士とか、この周りには古着屋がいっぱいあったから」
米原「なんかね、小さい古着屋さんが原宿にいっぱいあったよね。でも元々はデザイナーじゃなくて、ヘアメイクを目指していたという話を聞いたんだけど本当?」
北村「そうそう。小中学校から仲の良かった友達が高校を中退して美容師になって、ヘアメイクアーティストの野村真一さんが当時やっていた『アトリエシン』のメンバーになったんだよね。で、彼から『ミュージシャンの〇〇と会った』とか、『スタジオで〇〇の撮影した』とかそういう話を聞いてて。僕は中学校くらいからずっとロックを聴いて育ってたんで、美容師になればミュージシャンと仕事できるのかなってその時思ったんだよね(笑)。だから最初は美容学校に行くって決めてた。でも結局は、モード学園の方を選んだんだけどね。よく行く中古レコード屋が近くにいっぱいあったから」
 NOBUHIKO KITAMURA。1962年、東京都生まれ。東京モード学園を卒業後、株式会社オゾンコミュニティに入社。同年21歳で、ファッションブランド「HYSTERIC GLAMOUR(ヒステリックグラマー)」をスタート。ロックとファッションの融合をいち早く見出したコレクションを提案する。また、ソニック・ユースやプライマル・スクリーム、パティ・スミス、コートニー・ラブをはじめとし数多なアーティストたちと親交が深いことでも知られる。
NOBUHIKO KITAMURA。1962年、東京都生まれ。東京モード学園を卒業後、株式会社オゾンコミュニティに入社。同年21歳で、ファッションブランド「HYSTERIC GLAMOUR(ヒステリックグラマー)」をスタート。ロックとファッションの融合をいち早く見出したコレクションを提案する。また、ソニック・ユースやプライマル・スクリーム、パティ・スミス、コートニー・ラブをはじめとし数多なアーティストたちと親交が深いことでも知られる。
米原「基本的にずっと音楽なんだよね、モチベーションが。音楽を好きになったきっかけは何だったの?」
北村「最初は中学校の頃かな? 同級生たちの影響だね。下敷きにKISSだったりとか、好きなアーティストの写真を挟んだりしてて、それがきっかけだと思う」
米原「自分でバンドやったりとかはしてたの?」
北村「中学生の頃にちょろっと。でもやっぱり周りにもっとうまい連中たちがいたから、自分は演奏する側より聴く側がいいなって」
米原「そこからモード学園に入学し、怒涛の…?(笑)」
北村「怒涛の…だね(笑)。元々学校は4年制だったんだけど、僕は早く卒業したかったから夜間の授業も取っていて、その時に演出家の若槻善雄くんと出会った。彼は2年間で卒業して、ショーの演出をする会社で働き始めて、僕も在学中にそこでアルバイトを始めたんだよね。その頃にオゾンコミュニティで、デザイン画を描くアルバイトも始めていて。3年間学校行ってたけど、最後の1年はショーのバイトとスタイリストのアシスタントと、デザイン画のバイトが中心の生活だった。そんなこんなしてたらオゾンコミュニティから『新しいブランドやりたいんだけどお前ちょっとやってみないか』って言われて。それがちょうど学校を卒業した21歳のときだった」

米原「で、84年にはヒス(ヒステリックグラマー)立ち上げ。元々コンセプト自体は決まっていたの?」
北村「いや、全然決まってなかったですね。デザイン画のバイト自体もいい小遣い稼ぎというかそんな感じで、まぁそれもほとんどレコードに費やしてたんですけど。でもその中で、自分がデザインしたアイテムの何個かがすごい売れて、それもきっかけになってブランド始めようかってなったみたいな」
今でいうSNSが、当時はみんなが集まるクラブだった。
米原「色々海外との交流もあったり、その英語力がすごいなぁって思うんだけど。元々英語は喋れたの?」
北村「いや、全く。学生時代は英語は大の苦手だった。だけど21でヒスを始めて、英語を使う機会はたくさんあるから、ゆくゆくは英語を勉強しないとダメだなとは思っていて。ちょうどその時、コレクションで出会ったモデルの男の子が、うちで一緒に住むようになったんだよね。とりあえず一緒にいれば何か喋らなきゃいけないんだけど、最初の2日間くらいはなんの会話もなかった(笑)。でもだんだん辞書で調べながら喋るようになって、最終的には23歳から27歳までそいつとそいつの友達と一緒にいたね。他にも海外から来たモデルとかとクラブで仲良くなって居候したりもして、多い時には5、6人で住んでた。家の中では英語しか喋れないし、会社にもイギリスから訪ねてきたやつが入ったから、そうすると必然的に会社でも英語喋らなきゃならなくなって」
米原「その当時、日本人の友達とは遊ばなかったんだ?」
北村「うん、あえて遊ばなかったね。今みたいに世界も『TOKYO、TOKYO』って感じじゃなかったし、やっぱりロンドン、パリ、ニューヨークだったんだよね。だからその頃はコンプレックスもあったのかな、『なんで俺日本に生まれて来ちゃったんだろう』って。当時はニューヨークとかパリに住み始める友達も周りに多くて、自分も本当はそうしたかったんだけどね」
米原「行かなかった理由は?」
北村「ブランドが始まっちゃってたしね。みんなに迷惑かかるし、だったらそういう状況を東京で作ればいいかなって思ったんだよね。それで外国人の仲間と遊ぶようになって、本当それこそマーク・ジェイコブスとか。まだ彼がカメラマンのアシスタントをしてた時、西麻布とかで朝方まで飲むメンバーの一人でしたね」

米原「西麻布だと、どこによく行ってたの?」
北村「レッドシューズとかかな。ディスコからカフェバーになって。今、青山にもレッドシューズってあるんですけど、先代のオーナーが西麻布交差点のところでやってたんですよ。そこには当時、業界人の人とかも結構来てて」
米原「ね、来てたね。そういう場所だったよね」
北村「あとは、原宿のモンクベリーとか」
米原「モンクベリーっていうクラブが明治通りにあってね」
北村「地下1階がバーで、2階がダンスフロアになってて。あの当時クラブに通うんですけど『月曜日はどこ火曜日はどこ』って暗黙の了解で決まってて、そこに行かないと話にならなかった。そこが今でいうFacebookとかLINEのグループみたいな感じで、そこ行かないと今何が起きているのがわからなかったんだよね」
米原「そうそう。だから海外行ってる友達とかも帰ってくるとだいたいそういうところにいたよね。そこで、これから何がくるらしいとか流行ってるらしいとか話聞いたりしてね」
北村「実際、よねちゃん(米原さん)と会ったのもそういう現場だったしね」
「SNSカルチャー」も一つのカルチャー。
北村「それが今ではLINEでパパッとメッセージ送って友達になれたりできるんだもんね」
米原「でもこないだも話したけど、そのことを否定している訳でもないんだよね。逆に新しい革命が起きたってことだから、そこはついて行かないとって考え方だね」

北村「SNSとか携帯に依存しているのは若い子だけじゃなくて大人もみんなそうなんですよ。うちらの時代は時代で、パンクカルチャーがあったりとか、もう一つ前にはヒッピーカルチャーだとか色々あったのと同じ流れでの『SNSカルチャー』な訳だよね。だからそこは絶対に否定できない」
米原「その当時って、そこに行かないとダメで家の中にこもるってことがなかなか無かったからね。こもっちゃうともうアウトだった。とにかく外に出なきゃで」
北村「昼間はレコード屋に行って音の情報を探して、その帰りに古着屋に寄って何かレアなアイテム見つけて、夜はクラブ行って朝方に帰って仕事行ってみたいな」
米原「体力あったよね(笑)」
北村「あったよね、でもそうしないと世の中楽しめなかった」
米原「だから本当にクラブに行かないと世の中から置いて行かれてる感じあったもんね。ちょっと1週間行かないだけで、すごい置いて行かれたような気がしてた」
北村「でも結局23歳から27歳までの間、共同生活した外国人の仲間とか、後々の仕事に繋がっている人達とか、そういう人たちと出会ったのもそういう場所だったんだよね」
米原「確かにそうだったよね」

北村「そして、あの時代のイギリスから来てる連中は今の裏原とかあの辺りに、ものすごい貢献してるよね。GIMME FIVEのマイケル・コッペルマンとか」
米原「マイケルは本当に、日本文化をヨーロッパの方に教えてくれた人だよね」
北村「ちょうど94年くらいかな? STUSSYが日本に来日して、でちょうどそのSTUSSYのロンドンのディストリビューターをやってたのが、GIMME FIVEのマイケル・コッペルマンで。後に、藤原ヒロシ君とかと一緒に、ロンドンにブランドを展開したりしてね」
あの頃よりボーダレスになった原宿
北村「僕らが10代や20代の頃も、原宿って若者の街だったけど、当時の僕たちがロンドンとかニューヨークに行くと確実に負けて帰ってくるんですよ。歩いている人の装いもそうだし、クラブに行けば音楽もだってそう。いろんなところで『負けてんじゃん』って思うんです。でも今はどっちかっていえば『東京がナンバーワン』になってる。知ってる限りでは、アメリカ・ヨーロッパ圏の連中で東京を嫌いなやつっていないよね。若い世代も、俺ら世代にも」
米原「うん、確かにいないかもしれない」
北村「自分らが80年代頃、ロンドン・パリ・ロサンゼルス・ニューヨークに憧れてた感覚が、今では逆になってるのかなって。それは原宿の街を歩いてても感じる。例えば、バブルの頃はパリに行くと、日本人のツーリストがブランド物買い占めてたりとかしていたけれど、今はそれがまったく逆になってる気がする」
米原「でもさっきも(北村さんと)話していたんだけど、昔は原宿にも『そこに住んでいる人とか働いている人の為のお店』ってあったんだけど、今はどれも大きなお店になっちゃっていて、観光地化している感じはあるよね」
北村「でも、それもこれから受け入れていかなきゃいけないんじゃない?多分、東京オリンピック終わったとしても、この街にいる人の数は変わらない気がするしね」
米原「そうだね。でも寂しいのも確かだよね。昔よりも熱気が感じられない部分もあったりするから」
 トークショーの後は、スナックタイム。米原さんがカラオケを熱唱した
トークショーの後は、スナックタイム。米原さんがカラオケを熱唱した
北村「うん、でも僕らが10代や20代の時ってこの街に『壁』がいっぱいあった。音楽にしてもロックの中でも色々ジャンルが細かく分かれていて、それぞれに属している仲間が、いつも決まった遊び場で遊んでいるみたいな文化もあって。あとは年齢や性別もそうで、色々な線が引かれていた気がする。でもここ最近はそれがボーダレスになっていて、下手すれば男女も国籍も関係なく、どんなファッションでも関係ない。そういうのはすごくいいのかなって」
米原「確かにそれはあるかもしれないね」
北村「あとは何かもう一つアクションというか、今の若い子たちのムーブメントをもっともっと外に伝える力があったらいいなって。SNSとかも大きな武器になるし、それでいてもっとアナログなところでも何か起きたらいいなって。例えば、よく109系ブランドとかである、読者モデルからデザイナーになるとかもいいんだけど、その場合洋服作りの工程の部分は丸投げとか多いんですよ。別にいいんだけど、それは『洋服をクリエイトする』という次元には達していないと思う。まぁそんな面倒臭いことも惜しまないでやってみて欲しいってことですね」
米原「そうだね。ということで、今日はヒステリックグラマーの北村信彦さんをゲストにお話をお伺いしました。北村さん、本日はありがとうございました!」
 スナックタイム中の北村さん。若者たちからの質問に答えたり、情報交換したり
スナックタイム中の北村さん。若者たちからの質問に答えたり、情報交換したり
お酒を飲みながら、若者たちとフランクに話すお二人がとっても印象的でした。世代を超えて”ファッション”や”カルチャー”の話ができるこの時間も「スナックよね」の醍醐味の一つ。

以上、80年代から現在までのファッションカルチャーを熟知する2人のトークショーレポートでした。原宿に存在したクラブカルチャー、現代の原宿に求めるもの…熱気を感じる様々なお話をうかがえました。OMOHARAREALは今後も「スナックよね。」を追っていきますので、乞う期待!!
Text:miwo tsuji
Photo:Hiroaki Noguchi








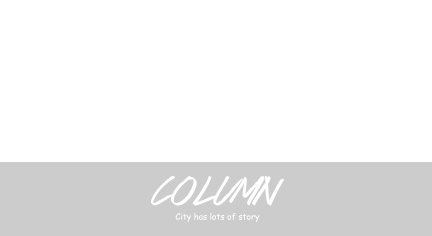


















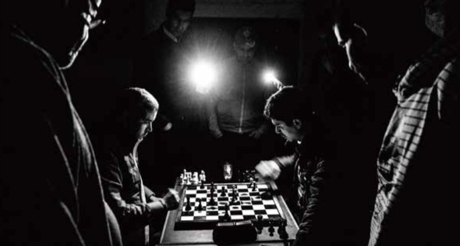











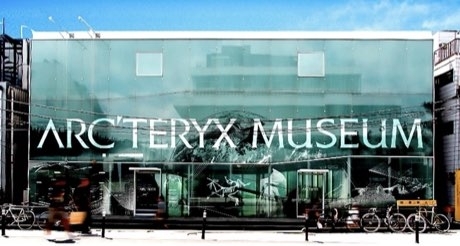



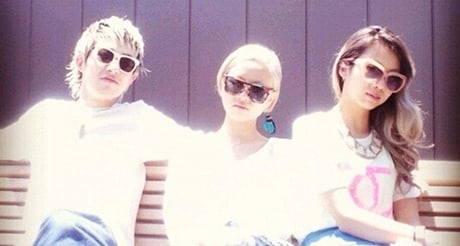
 会場:
会場: