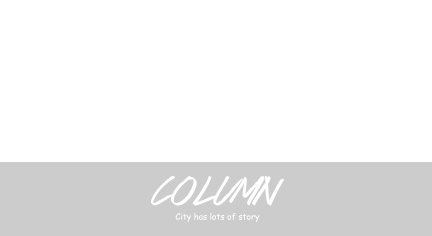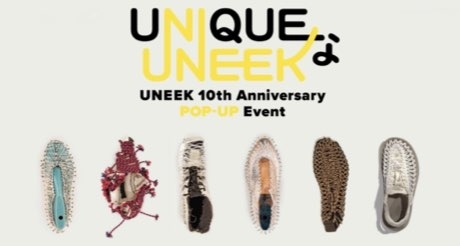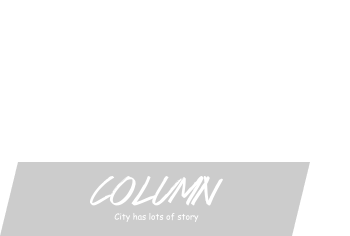人影もまばらな静かな住宅街、原宿。1960年代、1970年代の「まちの風景」
「1960年代の原宿、とても懐かしいなぁ。今からは想像できないほど、静かな街でした」
生まれも育ちも新宿。生粋のシティボーイだった設楽氏にとって、原宿は10代の頃から身近な街だった。当時の原宿周辺の様子を尋ねると、明治神宮に参拝するための”正月の街”という印象で、夜になると人っ子ひとり通らないような静かな住宅街だったそうだ。
「どことなくアメリカンな香りが漂う街。小さいながらに、そんなイメージもありましたね」
聞けば当時、同エリアにはアメリカ軍属の住宅地「ワシントンハイツ」があり、そこに住む人たちが贔屓にしていたキデイランドやオリエンタルバザーは今よりずっとアメリカンな雰囲気だったそう。新宿文化圏で生まれ育った設楽氏にとって10代前半の頃の原宿は、米軍関係者が主に入居していた「原宿セントラルアパート」(1960年)、ワシントンハイツの跡地にできた東京オリンピック選手村(1964年。現・代々木公園)、日本初の億ションとして話題になった「コープオリンピア」(1965年)の誕生など、どの街ともなにか違う”ちょっと不思議な住宅街”だった。

そして時代は1970年代へ。ベトナム戦争が終焉し、学生運動が下火になり、世の中のムードが変わりはじめた1970年代初頭、大学生になっていた設楽氏は「新宿のジャズ喫茶」から「湘南のサーフィン」に遊び場を変え、突然青空が広がったような”世の中の気分”を感じながら、大学時代を謳歌した。
「学生運動で大学が休講になった日は、晴れていたら湘南にサーフィンをしに行くことも多々。ひとしきり波に乗ったら、ボロの中古車で東京へ。帰る道中、青山通りを曲がって明治通りのほうに車を走らせていると、表参道からスコーンと抜けた景色が広がり、目の前に太陽があって。その景色を見て『なんかいいなぁ』と。いまと違い、当時の原宿は並木よりも高い建物を建てられない規制があり、そんな景色を楽しむこともできたんです」
湘南や横須賀のベースキャンプで遊び、アメリカの生活を目の当たりにする大学時代を過ごし、電通に入社。時は1975年、アイビーでもサープラスでもなく、質実剛健なアメリカのファッションを紹介したスクラップ・ブック『Made in U.S.A catalog』が発刊された年でもあった。
「広告代理店で働きながらも、家業(輸送用パッケージの製造会社)の経営不振もあり、父と話し合った結果、多角化のひとつとして小売ビジネスに目をつけました。勝負するなら自分が欲しいものを売ってみたいと思い、学生時代に憧れていたアメリカのライフスタイルを伝えられるような店のオープンを検討しました。コンセプトはアメリカンライフショップ。服屋をはじめるというよりUCLAの学生の部屋をつくるイメージでした。キーワードはUCLA。スタジャン、Tシャツ、スウェット、ジーンズ、スニーカー、スケボー……1976年、原宿に6.5坪のBEAMS第1号店をオープンしました」
 現在の「ビームス 原宿」が入っている、建物の一画に出店された「BEAMS 1号店」(1976年)
現在の「ビームス 原宿」が入っている、建物の一画に出店された「BEAMS 1号店」(1976年)
なぜ原宿を選んだのか。その理由は設楽氏の中で明白だった。聞けば当時の原宿は、いまのようなファッションタウンではなく、お店自体がほとんどないエリア。竹下通りに3軒、原宿セントラルアパートに小さなブティック、同潤会アパートの近くに数軒のアパレルショップ、キラー通りにはNICOLEとHOLLYWOOD RANCH MARKETの前身の極楽鳥があるほどだった。ラフォーレ原宿もまだ誕生しておらず、東京中央教会が建っていた。言わずもがな、第1号店を構えたエリア(現・ビームス原宿)には地元民以外、歩く人の姿はまばら。しかし不安はなかったそうだ。
「当時、若い風俗文化が夜から昼になってきているなぁと感じていました。そんな頃、文化をリードしていた人たちが原宿セントラルアパートを中心に、原宿に集まりはじめていたんです。新しい感性をもった若者にチャンスを与えてくれるような“昼の風”が原宿に吹いてきていて、小さなマンションブランドが次々に誕生するような機運もありました。やるなら今だ。小さな店を、百貨店のない街に出そうと思った」
 神宮前タワービルディング、ビームスオフィス内の社長室から望む原宿の街。竹下通りが見渡せる。2017年、このパレフランス跡地にできたビルの開業とともに、ビームスはオフィス機能を集約。新オフィスも話題となった。
神宮前タワービルディング、ビームスオフィス内の社長室から望む原宿の街。竹下通りが見渡せる。2017年、このパレフランス跡地にできたビルの開業とともに、ビームスはオフィス機能を集約。新オフィスも話題となった。
当時を振り返り、「オープンの時、表参道との交差点でショップ案内のチラシを配ったんですよ」と、懐かしそうに話す設楽氏。時は進み、1980年代、1990年代、2000年代へ。BEAMSの躍動が始まる。
【次のページ】>>原宿は「時代を映す鏡」。時代ごとに若者が集まり、新しい文化が生まれたワケ