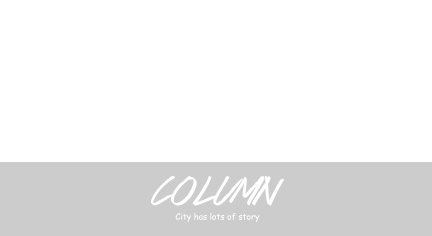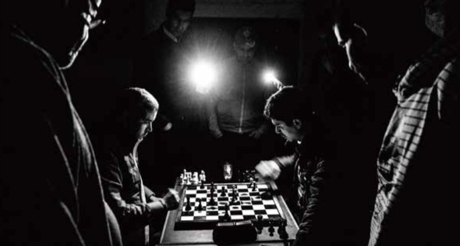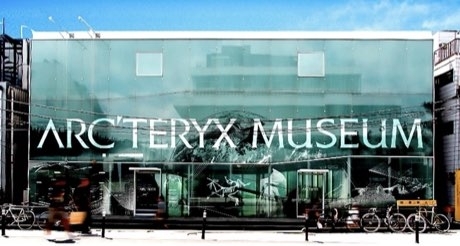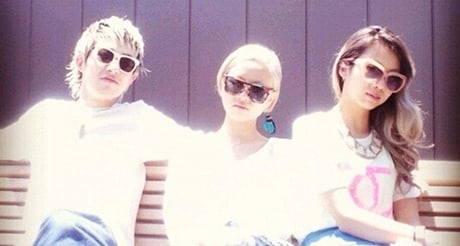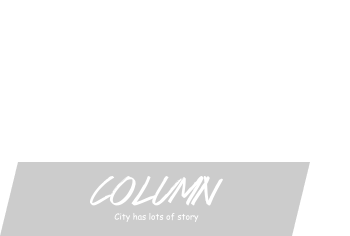「地道な対面のコミュニケーションに勝るものはない」

普段はあまり気にしていないものの、いざゴミ拾いをするとなると、タバコの吸い殻、空き缶やペットボトルなど予想以上にたくさんのゴミに毎回驚く。
元気さんがキャットストリートでゴミ拾いを始めるよりも以前。9〜10年前くらいはストリートスナップが最盛期を迎えていた。元気さんはスナップハンターとして原宿の街に接続していた。裏原側の古着屋によく立ち寄っていたという。学生を卒業する頃になり、ふと思い浮かんだのは今まで慣れ親しんできた原宿の街のことだった。
「社会人になったときにスーツを着る仕事に就いた場合、洋服を着る機会が途端に少なくなる。原宿に買い物に来なくなるわけです。実際、社会人になった瞬間に表参道・原宿に来なくなる人も多い。それだけは絶対に嫌だなと思った」

車両には注意しつつ、この日は100人以上の参加者で端から端まで広がりローラー作戦のようにゴミを拾った。圧巻の光景だ。
かといって、買い物に来るだけになってしまっても味気ない。消費活動以外で地域と関わりながら居心地が良いと思える場所を作っていきたいという思いが、キャットストリートでのクリーンアップ活動につながっているのだ。普通買い物に来るのが“当たり前”のエリアで、“当たり前”じゃないこと(=クリーンアップ)をしに来るという、「CATs ACT DIFFERENT」の精神がCATsクリーンアップのベースにはある。そんなクリーンアップの初回の参加人数はどうだったのだろうか?
「最初は“1回目”なのか単発のイベントなのかわからないから、人数はそれなりに集まりました。2回目からは参加人数がグッと減りました。でも人数は少なくてもいいやって割り切ってましたね。無理なく続けていくことが大事だなと。掃除や環境問題とか、それ自体が目的となってしまうと来たくなくなってしまう。時間があるから楽しみにくるくらいでちょうどいい。買い物以外の理由でキャットストリートに来て、ついでにゴミを拾うくらいの感覚ですね。」
 オープンな雰囲気は、活動全体に波及。参加者は肩肘張らず、その時だから出来る会話を楽しみつつ、ゴミを拾う。
オープンな雰囲気は、活動全体に波及。参加者は肩肘張らず、その時だから出来る会話を楽しみつつ、ゴミを拾う。
およそ9年間という歳月をかけて100回の活動を続けてきた元気さん。続けていく上でどんなところに苦労したのか、辛かったことなどはあるのかを尋ねた。
「辛くはないけど、地道なことの積み重ねでした。始めた当時は学生だったから時間があったのでひたすら自分の足で周辺のお店を回って、世間話をして『こういう活動しているんですよ』って周知してもらっていましたね。今でこそ勝手に情報を共有してくれる人がいて、集まってくれるようになりましたけど、最初はビラを配ったりしてましたし、地道な対面のコミュニケーションに勝るものはないです」。
【次のページ】>>「コミュニティはもともとあった」3.11の教訓