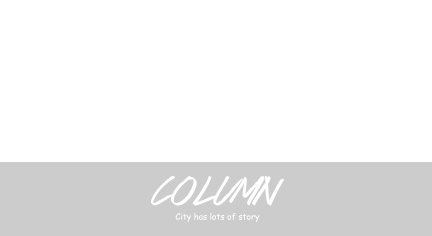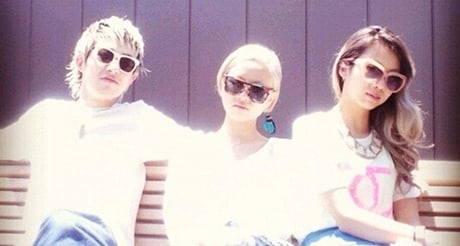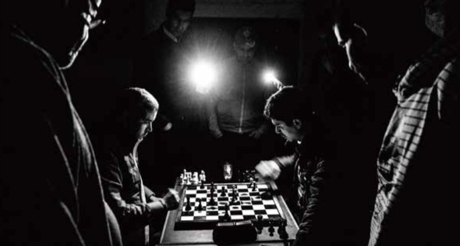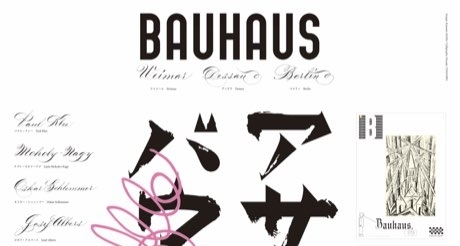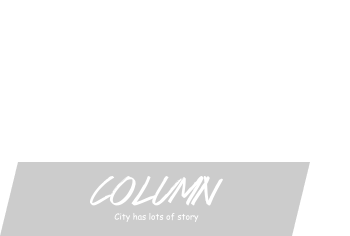現在の表参道の生みの親?景観と文化との共生
それぞれの立地を活かし、都内を中心に16カ所に建設された同潤会アパートメント。なかでも同潤会青山アパートメントは、道路に面した街路型という独特のつくりをしていた。これは、明治神宮に向かって伸びる表参道が街の中心を通っており、建物の敷地が道路に面して細長いものであったためだ。その結果、アパートメントは街路に沿うように建ち並ぶこととなった。6棟が一列に並び、その裏手に4棟が中庭を囲むようにして建てられた。

2002年当時の「同潤会青山アパートメント」。道路に面した街路型で3階建てに統一され、ケヤキ並木と同じ高さで建てられていることがよく分かる。
写真:裏辺研究所 日本の旅 同潤会青山アパート~東京都渋谷区~
10棟すべてが3階建てに統一された景観は、明治神宮と大きな関わりをもって形づくられていった。1923年(大正14年)に同潤会青山アパートメントの土地が買収された頃、1920年(大正9年)に創建の明治神宮の整備が並行して行われていた。
そのため、天皇陛下が表参道を通られた際に見下ろすような建物をつくるのは不遜だと、同潤会青山アパートメント建設に近隣住民から反対の声が上がっていたという。そこで、高層ではなく3階建ての比較的低いつくりに抑えられたのだ。
そのほかにもさまざまな工夫がなされた。参道から洗濯物が見えないように屋上の外壁を高くしたり、アパートメントを歩道よりも下げて建物の前に植樹を行い、建物からの圧迫感を取り除くといった徹底的な景観保護の対策がなされていた(当時、参道側に洗濯物を干さないよう指導もされていたという)。
ちなみに、ほかの同潤会アパートメントには1階部分に店舗付きの住戸があったが、同潤会青山アパートメントは一切用意されなかった。これも景観づくりの一環と考えられる。
こうした景観への高い意識を元につくられた同潤会青山アパートメントが、以降の表参道に建てられる建築物の規範となったことは自然な流れだろう。現在も表参道沿いに高層の建築物が少ないのも、こういった景観への意識が脈々と受け継がれているからだ。

2021年12月現在、OMOHARAREAL編集部撮影の表参道ヒルズと欅並木。
大げさではなく、現在の表参道沿いの街並みは、このアパートメントから始まったといえる。いまの表参道の姿は、同潤会の建築群があってこそなのだ。
 2002年12月。ショップやギャラリーが入居する同潤会青山アパートメントと表参道の欅並木。
2002年12月。ショップやギャラリーが入居する同潤会青山アパートメントと表参道の欅並木。
建設時から一貫して景観を意識してつくられた同潤会青山アパートメント。表参道がファッション街となってからも、住居としての建物から、ブティックやギャラリーなどが入居する建物に姿を変えていった。時代が変わるにつれて、建物自体の在り方も変わっていき、街の変化とも調和して存続していた。
しかし、同潤会青山アパートメントは大正時代から80年以上建ち続けた歴史を歩んだゆえ、建物に限界が迫っていた。老朽化の激しいアパートメントの復旧は労力的にも経済的にも非常にシビアで、そのままの形で残すことは現実的ではなかった。
【次のページ】>>形を変えて受け継がれる同潤会青山アパートメント